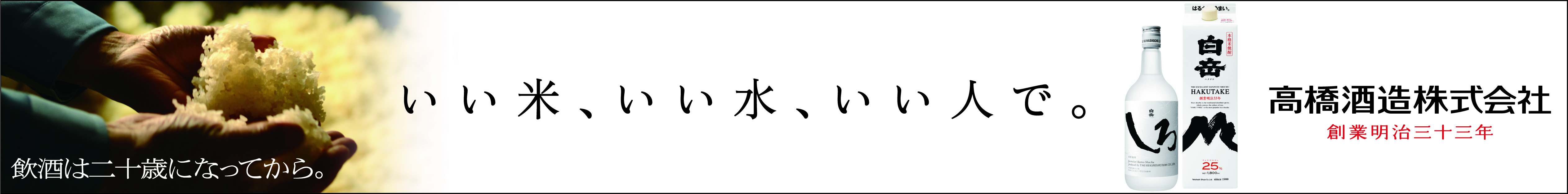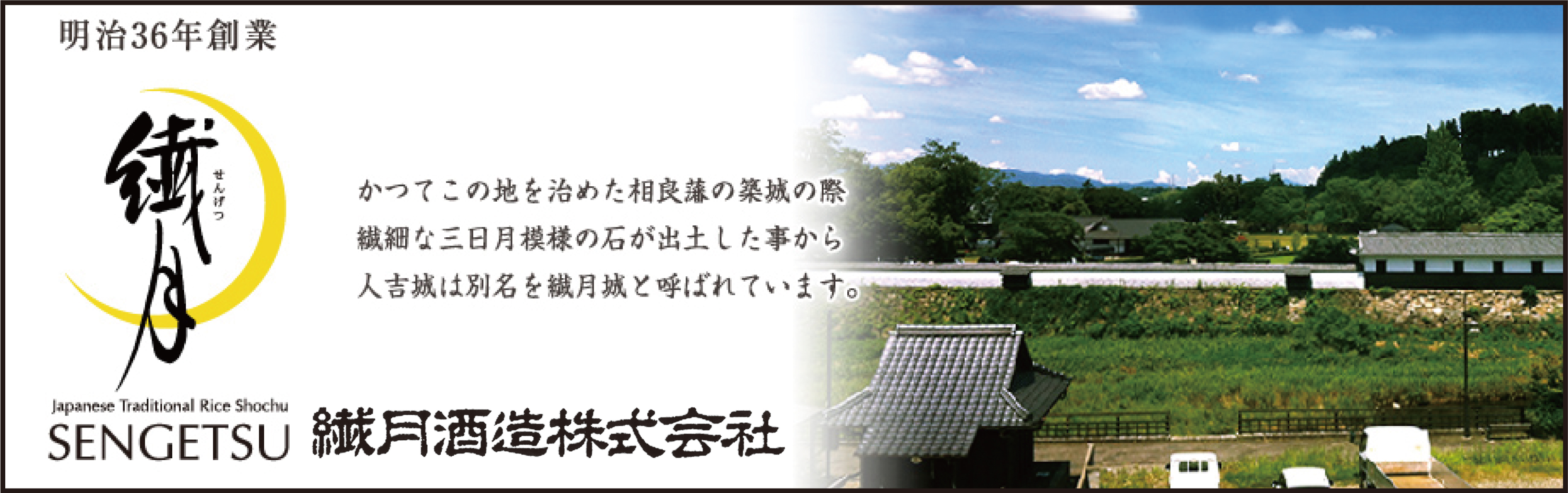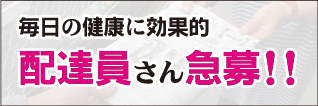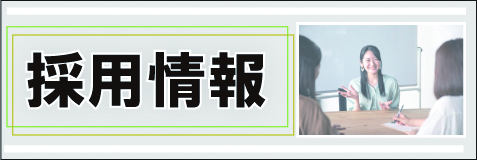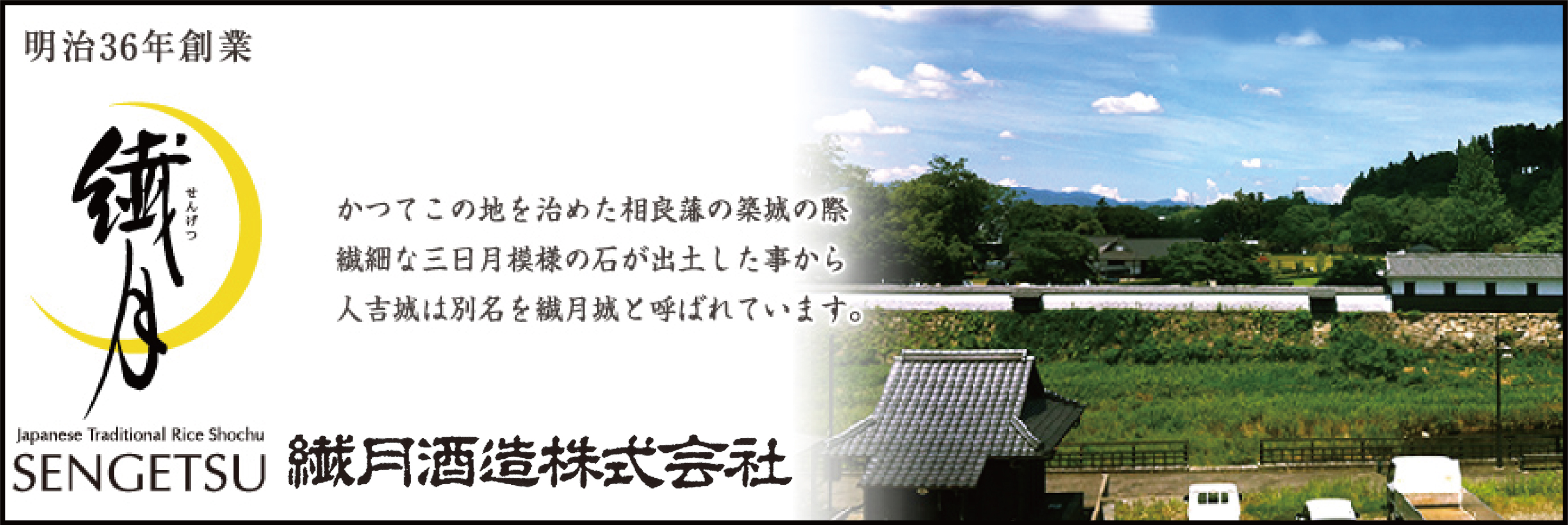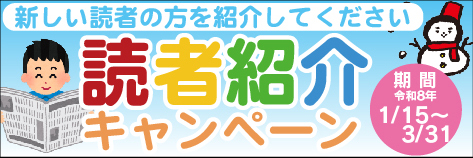更新履歴
| 特集 | 球磨中央高校CS班開発アイス携え日韓交流へ(土曜レポート) | 2026/02/28 |
| ニュース | 多良木町「ゑびす植木市」開幕 苗木や花類など多種多彩 | 2026/02/28 |
| ニュース | “海と森の恵み”一堂に あすまで球泉洞でフェア | 2026/02/28 |
| ニュース | 公共施設を包括管理委託 9年度から71施設に導入 人吉市 | 2026/02/28 |
| ニュース | 華道家元池坊人吉支部のいけばな展「春の鼓動」始まる | 2026/02/28 |
| 瀬音 | 瀬音を更新しました | 2026/02/28 |
| 週間ガイド | 週間ガイドを更新しました | 2026/02/28 |
| ニュース | 海外に輸出するには? 豊永酒造が経験発表 | 2026/02/27 |
| ニュース | 整備のあり方 改めて検証 新ごみ処理施設 | 2026/02/27 |
| 瀬音 | 瀬音を更新しました | 2026/02/27 |
| ニュース | 人吉下球磨消防組合 移転運用開始 12年度へ | 2026/02/26 |
| ニュース | 公共交通で買い物支援 県立大生「KUMAJECT」 | 2026/02/26 |
| 瀬音 | 瀬音を更新しました | 2026/02/26 |
| ニュース | 人吉市議会定例会開会 松岡市長が施政方針表明 | 2026/02/25 |
| ニュース | 駅のにぎわいづくりへ 球磨工業高校がパートナー校に認定 | 2026/02/25 |
| ニュース | 「球磨川リバーミュージアム」構想 人吉でキックオフフォーラム | 2026/02/25 |
| 瀬音 | 瀬音を更新しました | 2026/02/25 |
| 特集 | 田代 利一さん(話題の人にインタビュー) | 2026/02/24 |
| ニュース | 万江川流域の災害防止へ 山江村屋形地区の砂防えん堤整備に着工 | 2026/02/24 |
| ニュース | 人吉CPは「建て替え」 大ホール改修見送る | 2026/02/24 |